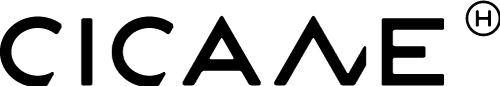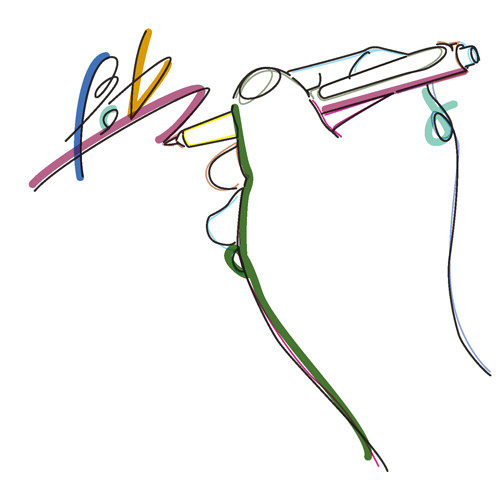【街の流線(第1回)】
午後2時。平山俊嗣は炎天下のオフィス街をひとりで歩いていた。
ビルから伸びた影の内を選んで歩きながら、昨晩の天気予報が、あすの最高気温は37度にまで達する、と告げていたことを思い出していた。
直前には、緑のベースボール・キャプを目深に被り、ユニフォームのポロシャツの袖を肩まで捲って、大きな荷台を引く自転車を黙々と漕ぐ配送員の男とすれ違ったりもした。
思いの外、といっては失礼だが、汗だくの彼らが無臭なのは何故だろう。
いつからかそんな風に、盛夏の肉体労働者やスポーツマンに感心することが、平山にとって密かな夏の風物詩となっていた。
加えて、ビルとビルの間を渡るときなど、影が途切れて身体が直射日光に曝されると、小学3年生の夏休みに没頭したアーケード・ゲームのことを思い出す癖も、平山にはあった。
体力の残量を示す真紅のゲージが、悪の日射しの攻撃を受けて黄変し、やがて、透過していく。
ゲージが目減りすることは、夏休みが、そして人生が終わりに近づくことを彼に想起させ、ポケットの中に残るコインの数は我が余命そのものである、とすら思わせた。
そんな幼き日の絶望的世界観が32歳の平山を侵しつくす直前、目的地のコーヒー・スタンドの入り口、緑と白の、縦ストライプの幌の下へとたどり着いた。
(つづく)